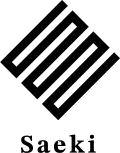おふたりさまの相続手続き
相続財産の分配に関する手続きの流れをご紹介します。
それ以外の事務についてはおひとりさまの死後事務委任内容をご覧ください。
相続手続きの流れ
相続開始後、①~③について速やかに調査を開始します。④の期限まで3ヶ月しかないため、並行して行う必要があります。
「遺産分割協議」について詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
その他、期限のある手続きは以下の通りです。
- 所得税の準確定申告 (4カ月以内)
- 相続税の申告 (10ヶ月以内)
- 遺留分侵害額請求 (1年以内)
- 相続登記 (3年以内)
手続きの解説
遺言書の有無の確認
遺言書の有無で相続の手続きは大きく変わります。
公正証書遺言であれば公証役場で原本の検索を行うことができ、自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は法務局で検索を行うことができます。
それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言は自宅などを探してみましょう。
公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度利用の場合
検認は不要ですので、遺言書の効力を確認して遺言書通りに遺産分配の手続きを行います。もし、遺言書の内容に従わない遺産分配を行う場合には、遺産分割協議が必要となります。
また、遺言書に記載のない財産がある場合は、その財産について遺産分割協議の必要があります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合
家庭裁判所に検認の申し立てを行います。検認が終わるまで、決して開封してはいけません。検認完了後は上記と同様の手続きを行います。
相続人の確定
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を収集し、内容を解読して相続人を確定します。
単純で簡単な作業に聞こえそうですが、人数が多い場合や代襲相続が発生する場合は作業量が増え、時間もかかる大変な作業です。
相続人が確定したら、相続関係図を作成し、法務局で「法定相続情報一覧図」を申請・交付しておくと、いわゆる「戸籍の束」を持ち歩く必要がなくなり、以降の作業を行いやすくなります。
相続財産の調査
預貯金通帳や信用情報機関、名寄帳、パソコンやスマホの情報などから一つひとつ調査して、相続財産をすべて洗い出し、財産額を確定させます。
この作業も地味ですが、相続放棄・遺産分割・相続税申告の判断材料となるため、とても重要なものです。
特に、相続放棄・限定承認の申し立ては相続開始後3ヶ月以内に行わなければならないため、時間との勝負になります。調査が完了したら目録にまとめましょう。
- 「エンディングノート」を利用して財産情報を記載しておくことで、相続人のためにもご自身の整理にもなるのでおすすめです!
- 最近では、パソコンやスマホの中にしか情報がない場合もありますので、スマホやインターネットの解約には注意しましょう。
相続放棄・限定承認の検討
相続人全員に財産目録を送付し、各相続人は承認または放棄の判断をします。
相続放棄の申し立ては、各相続人が個別に家庭裁判所に行うことができます。
一方、限定承認の申し立ては、相続人全員で共同して行わなければなりません。熟慮期間である3ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認したものとなります。
遺産分割協議
相続人が全員参加で遺産分割協議を行い、全員が同意したら協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
相続財産の分配手続き
遺産分割協議が成立したら、相続財産の分配を行います。
預貯金や有価証券、不動産など、遺産の種類に応じて必要な手続きを行います。機関によって必要書類が変わる場合があります。
報酬額(税込み)
- 遺産分割協議書プラン
- 遺産分割協議の結果をまとめます。
- 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書
オススメ
- 調査もまとめてプラン
- 遺産分割協議までの業務をまとめて!
- 198,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
相続人5名、調査5機関まで。
- 相続丸ごとお任せプラン
- 相続手続きを丸ごとお任せ!
- 253,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
名義変更・解約等遺産の種類に応じて必要な手続き
相続人5名、手続き5機関まで。
個別の業務も承ります!お問い合わせください!
- 必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。
- 追加の作業が発生した場合、追加費用がかかる可能性があります。
- 不動産関連、相続税関連のご相談は提携先士業事務所をご紹介します。
- 紛争の恐れのある依頼はお引き受けできない場合があります。
遺言書の有無で相続の手続きは大きく変わります。
公正証書遺言であれば公証役場で原本の検索を行うことができ、自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は法務局で検索を行うことができます。
それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言は自宅などを探してみましょう。
公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度利用の場合
検認は不要ですので、遺言書の効力を確認して遺言書通りに遺産分配の手続きを行います。もし、遺言書の内容に従わない遺産分配を行う場合には、遺産分割協議が必要となります。
また、遺言書に記載のない財産がある場合は、その財産について遺産分割協議の必要があります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合
家庭裁判所に検認の申し立てを行います。検認が終わるまで、決して開封してはいけません。検認完了後は上記と同様の手続きを行います。
相続人の確定
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を収集し、内容を解読して相続人を確定します。
単純で簡単な作業に聞こえそうですが、人数が多い場合や代襲相続が発生する場合は作業量が増え、時間もかかる大変な作業です。
相続人が確定したら、相続関係図を作成し、法務局で「法定相続情報一覧図」を申請・交付しておくと、いわゆる「戸籍の束」を持ち歩く必要がなくなり、以降の作業を行いやすくなります。
相続財産の調査
預貯金通帳や信用情報機関、名寄帳、パソコンやスマホの情報などから一つひとつ調査して、相続財産をすべて洗い出し、財産額を確定させます。
この作業も地味ですが、相続放棄・遺産分割・相続税申告の判断材料となるため、とても重要なものです。
特に、相続放棄・限定承認の申し立ては相続開始後3ヶ月以内に行わなければならないため、時間との勝負になります。調査が完了したら目録にまとめましょう。
- 「エンディングノート」を利用して財産情報を記載しておくことで、相続人のためにもご自身の整理にもなるのでおすすめです!
- 最近では、パソコンやスマホの中にしか情報がない場合もありますので、スマホやインターネットの解約には注意しましょう。
相続放棄・限定承認の検討
相続人全員に財産目録を送付し、各相続人は承認または放棄の判断をします。
相続放棄の申し立ては、各相続人が個別に家庭裁判所に行うことができます。
一方、限定承認の申し立ては、相続人全員で共同して行わなければなりません。熟慮期間である3ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認したものとなります。
遺産分割協議
相続人が全員参加で遺産分割協議を行い、全員が同意したら協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
相続財産の分配手続き
遺産分割協議が成立したら、相続財産の分配を行います。
預貯金や有価証券、不動産など、遺産の種類に応じて必要な手続きを行います。機関によって必要書類が変わる場合があります。
報酬額(税込み)
- 遺産分割協議書プラン
- 遺産分割協議の結果をまとめます。
- 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書
オススメ
- 調査もまとめてプラン
- 遺産分割協議までの業務をまとめて!
- 198,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
相続人5名、調査5機関まで。
- 相続丸ごとお任せプラン
- 相続手続きを丸ごとお任せ!
- 253,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
名義変更・解約等遺産の種類に応じて必要な手続き
相続人5名、手続き5機関まで。
個別の業務も承ります!お問い合わせください!
- 必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。
- 追加の作業が発生した場合、追加費用がかかる可能性があります。
- 不動産関連、相続税関連のご相談は提携先士業事務所をご紹介します。
- 紛争の恐れのある依頼はお引き受けできない場合があります。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を収集し、内容を解読して相続人を確定します。
単純で簡単な作業に聞こえそうですが、人数が多い場合や代襲相続が発生する場合は作業量が増え、時間もかかる大変な作業です。
相続人が確定したら、相続関係図を作成し、法務局で「法定相続情報一覧図」を申請・交付しておくと、いわゆる「戸籍の束」を持ち歩く必要がなくなり、以降の作業を行いやすくなります。
相続財産の調査
預貯金通帳や信用情報機関、名寄帳、パソコンやスマホの情報などから一つひとつ調査して、相続財産をすべて洗い出し、財産額を確定させます。
この作業も地味ですが、相続放棄・遺産分割・相続税申告の判断材料となるため、とても重要なものです。
特に、相続放棄・限定承認の申し立ては相続開始後3ヶ月以内に行わなければならないため、時間との勝負になります。調査が完了したら目録にまとめましょう。
- 「エンディングノート」を利用して財産情報を記載しておくことで、相続人のためにもご自身の整理にもなるのでおすすめです!
- 最近では、パソコンやスマホの中にしか情報がない場合もありますので、スマホやインターネットの解約には注意しましょう。
相続放棄・限定承認の検討
相続人全員に財産目録を送付し、各相続人は承認または放棄の判断をします。
相続放棄の申し立ては、各相続人が個別に家庭裁判所に行うことができます。
一方、限定承認の申し立ては、相続人全員で共同して行わなければなりません。熟慮期間である3ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認したものとなります。
遺産分割協議
相続人が全員参加で遺産分割協議を行い、全員が同意したら協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
相続財産の分配手続き
遺産分割協議が成立したら、相続財産の分配を行います。
預貯金や有価証券、不動産など、遺産の種類に応じて必要な手続きを行います。機関によって必要書類が変わる場合があります。
報酬額(税込み)
- 遺産分割協議書プラン
- 遺産分割協議の結果をまとめます。
- 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書
オススメ
- 調査もまとめてプラン
- 遺産分割協議までの業務をまとめて!
- 198,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
相続人5名、調査5機関まで。
- 相続丸ごとお任せプラン
- 相続手続きを丸ごとお任せ!
- 253,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
名義変更・解約等遺産の種類に応じて必要な手続き
相続人5名、手続き5機関まで。
個別の業務も承ります!お問い合わせください!
- 必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。
- 追加の作業が発生した場合、追加費用がかかる可能性があります。
- 不動産関連、相続税関連のご相談は提携先士業事務所をご紹介します。
- 紛争の恐れのある依頼はお引き受けできない場合があります。
預貯金通帳や信用情報機関、名寄帳、パソコンやスマホの情報などから一つひとつ調査して、相続財産をすべて洗い出し、財産額を確定させます。
この作業も地味ですが、相続放棄・遺産分割・相続税申告の判断材料となるため、とても重要なものです。
特に、相続放棄・限定承認の申し立ては相続開始後3ヶ月以内に行わなければならないため、時間との勝負になります。調査が完了したら目録にまとめましょう。
- 「エンディングノート」を利用して財産情報を記載しておくことで、相続人のためにもご自身の整理にもなるのでおすすめです!
- 最近では、パソコンやスマホの中にしか情報がない場合もありますので、スマホやインターネットの解約には注意しましょう。
相続放棄・限定承認の検討
相続人全員に財産目録を送付し、各相続人は承認または放棄の判断をします。
相続放棄の申し立ては、各相続人が個別に家庭裁判所に行うことができます。
一方、限定承認の申し立ては、相続人全員で共同して行わなければなりません。熟慮期間である3ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認したものとなります。
遺産分割協議
相続人が全員参加で遺産分割協議を行い、全員が同意したら協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
相続財産の分配手続き
遺産分割協議が成立したら、相続財産の分配を行います。
預貯金や有価証券、不動産など、遺産の種類に応じて必要な手続きを行います。機関によって必要書類が変わる場合があります。
報酬額(税込み)
- 遺産分割協議書プラン
- 遺産分割協議の結果をまとめます。
- 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書
オススメ
- 調査もまとめてプラン
- 遺産分割協議までの業務をまとめて!
- 198,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
相続人5名、調査5機関まで。
- 相続丸ごとお任せプラン
- 相続手続きを丸ごとお任せ!
- 253,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
名義変更・解約等遺産の種類に応じて必要な手続き
相続人5名、手続き5機関まで。
個別の業務も承ります!お問い合わせください!
- 必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。
- 追加の作業が発生した場合、追加費用がかかる可能性があります。
- 不動産関連、相続税関連のご相談は提携先士業事務所をご紹介します。
- 紛争の恐れのある依頼はお引き受けできない場合があります。
相続人全員に財産目録を送付し、各相続人は承認または放棄の判断をします。
相続放棄の申し立ては、各相続人が個別に家庭裁判所に行うことができます。
一方、限定承認の申し立ては、相続人全員で共同して行わなければなりません。熟慮期間である3ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認したものとなります。
遺産分割協議
相続人が全員参加で遺産分割協議を行い、全員が同意したら協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
相続財産の分配手続き
遺産分割協議が成立したら、相続財産の分配を行います。
預貯金や有価証券、不動産など、遺産の種類に応じて必要な手続きを行います。機関によって必要書類が変わる場合があります。
報酬額(税込み)
- 遺産分割協議書プラン
- 遺産分割協議の結果をまとめます。
- 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書
オススメ
- 調査もまとめてプラン
- 遺産分割協議までの業務をまとめて!
- 198,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
相続人5名、調査5機関まで。
- 相続丸ごとお任せプラン
- 相続手続きを丸ごとお任せ!
- 253,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
名義変更・解約等遺産の種類に応じて必要な手続き
相続人5名、手続き5機関まで。
個別の業務も承ります!お問い合わせください!
- 必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。
- 追加の作業が発生した場合、追加費用がかかる可能性があります。
- 不動産関連、相続税関連のご相談は提携先士業事務所をご紹介します。
- 紛争の恐れのある依頼はお引き受けできない場合があります。
相続人が全員参加で遺産分割協議を行い、全員が同意したら協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
相続財産の分配手続き
遺産分割協議が成立したら、相続財産の分配を行います。
預貯金や有価証券、不動産など、遺産の種類に応じて必要な手続きを行います。機関によって必要書類が変わる場合があります。
報酬額(税込み)
- 遺産分割協議書プラン
- 遺産分割協議の結果をまとめます。
- 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書
オススメ
- 調査もまとめてプラン
- 遺産分割協議までの業務をまとめて!
- 198,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
相続人5名、調査5機関まで。
- 相続丸ごとお任せプラン
- 相続手続きを丸ごとお任せ!
- 253,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
名義変更・解約等遺産の種類に応じて必要な手続き
相続人5名、手続き5機関まで。
個別の業務も承ります!お問い合わせください!
- 必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。
- 追加の作業が発生した場合、追加費用がかかる可能性があります。
- 不動産関連、相続税関連のご相談は提携先士業事務所をご紹介します。
- 紛争の恐れのある依頼はお引き受けできない場合があります。
遺産分割協議が成立したら、相続財産の分配を行います。
預貯金や有価証券、不動産など、遺産の種類に応じて必要な手続きを行います。機関によって必要書類が変わる場合があります。
報酬額(税込み)
- 遺産分割協議書プラン
- 遺産分割協議の結果をまとめます。
- 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書
オススメ
- 調査もまとめてプラン
- 遺産分割協議までの業務をまとめて!
- 198,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
相続人5名、調査5機関まで。
- 相続丸ごとお任せプラン
- 相続手続きを丸ごとお任せ!
- 253,000円(税込)
- 相続人調査
相続関係説明図
法定相続情報一覧図
相続財産調査
財産目録
遺産分割協議書
名義変更・解約等遺産の種類に応じて必要な手続き
相続人5名、手続き5機関まで。
個別の業務も承ります!お問い合わせください!
- 必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。
- 追加の作業が発生した場合、追加費用がかかる可能性があります。
- 不動産関連、相続税関連のご相談は提携先士業事務所をご紹介します。
- 紛争の恐れのある依頼はお引き受けできない場合があります。