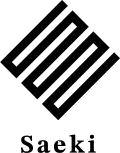おふたりさまの相続トラブル事例集
おふたりさまが安心して将来を迎えるために、知っておきたい相続の落とし穴について解説します。
要注意!「配偶者が全財産を相続」とは限りません
「私たちには子供がいないから、どちらかが亡くなったら、残された方が全財産を相続できるはず」
このように考えていらっしゃる、おふたりさまは非常に多いです。しかし、それは法律上の規定とは異なる場合があり、この誤解が相続トラブルの大きな原因となっています。
遺言書がない場合、亡くなった方に子供がいないときの法定相続人は、以下のようになります。
1:相続人が「配偶者」と「亡くなった方の親」の場合
亡くなった方の親御さんがご健在の場合、**法定相続人は「配偶者」と「親」**になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
たとえ親御さんが高齢で、「財産は要らない」と考えていたとしても、法律上は相続人であるため、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。また、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、親御さんがご自身の相続分を主張する背後に、その兄弟姉妹の意向が影響しているケースなども考えられます。
親には遺留分(法律で定められた最低限保証された取り分)があるため、全財産を確実に、とはいきませんが、遺言書を作成しておくことでより多くの財産を配偶者に遺すことが可能です。
2:相続人が「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹(甥姪)」の場合
亡くなった方の親御さんが既に他界されている場合、法定相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」になります。兄弟姉妹の中に亡くなっている方がいれば、その方の子供である甥・姪が代襲相続します。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹(甥姪)が合計で4分の1です。
兄弟姉妹や甥姪は、親の場合よりも人数が多くなったり、関係性がより疎遠だったりすることが一般的です。そのため、面識のない相続人や、遠方に住む多数の相続人と遺産分割協議を行わなければならず、協議が難航したり、感情的な対立が生じたりする可能性がより高まります。
このケースでは、兄弟姉妹(および甥姪)には遺留分がありません。そのため、遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と明確に指定しておけば、原則としてその通りに実現でき、兄弟姉妹等との遺産分割協議も不要になります。遺言書の有効性が非常に高い場面と言えます。
【まとめ】残される配偶者への「思いやり」としての遺言書
ここまで見てきたように、おふたりさまの場合、遺言書がないと、残された配偶者は、亡くなった方の親族(親や兄弟姉妹、甥姪)と遺産の分け方について協議する必要が出てきます。
ただでさえ、大切なパートナーを亡くした深い悲しみの中にあるときに、関係性の薄い、あるいは初めて会うような親族と、お金や財産の話をしなければならないのです。書類の準備や連絡調整だけでも煩雑なのに、もし意見が対立すれば、その精神的な負担は計り知れません。
「遺言書」を作成しておくことは、ご自身の意思を実現するためだけではありません。残される大切なパートナーに、このような相続手続きの負担や精神的なストレスをできるだけかけないようにする、「思いやり」の形でもあるのです。
特に、お互いに全財産を遺したいと考えるご夫婦には、夫婦相互遺言という選択肢もあります。
当事務所では、今治市にお住まいのおふたりさまの状況に合わせた遺言書作成や終活のご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。